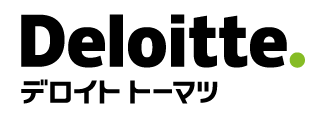SPI REPORT
効果的なマーケティング・コミュニケーション戦略の立案プロセス(エスピーアイ “Symphony” によるアプローチ:第2回/全5回)
第1回において、コミュニケーション戦略要素として5W2Hをご紹介しました。それではさっそくこれらをどのように決定/定義していくかについて、ご案内したいと思います。
今回のトピックは、「コミュニケーション目標(KPI)設定」と「ターゲット・オーディエンスの設定」です。これらは5W2H要素の“Why”と“To Whom”にあたります。
目的認識の統一
マーケティング・コミュニケーションの目的は、以下5つに分類することによってその後の思考の整理が容易になります。
- Awareness
- 広告活動やブランド名などの認知
- Knowledge
- 商品特性やブランド便益などの理解
- Image
- 望ましいブランドイメージや知覚品質などの浸透
- Response
- WEBやコールセンターへのアクセスなどの活動促進
- Trade Effects
- 業界内や小売、社内へのプレゼンスの確保
目的は一義に限るものではありませんが、複数設定の場合は、優先順位や重要度を持つことが必要となります。当然ながら、商品カテゴリーやブランドステージ、マーケティング目標の設定などの違いにより、導かれる仮説も異なってきます。
KPI設定のための詳細分析方法やケーススタディ紹介は別の記事に機会を譲りますが、エスピーアイは様々なデータ分析、およびクライアントご担当者との協議を通して要因間の因果関係を明らかにして、コミュニケーション目標設定のお手伝いをいたします。
これらの戦略的5分類を使用することにより、ステークホルダー内でのコンセンサス醸成や、コミュニケーション実施フェーズでの多岐にわたる活動の優先付け(予算配分)、活動提案への評価に一貫性を保つことが可能となります。また分類内でさらに詳細な項目別の具体的KPI数値を伴うことにより、活動の目標管理と説明責任を確保することが容易になります。
ターゲット・オーディエンスの設定
コミュニケーション目的がある程度明らかになると、続いてターゲット・オーディエンスの特定に進むことができます。
下に概念を示しましたが、まず現行顧客、競合顧客、新規消費者の3つの区分を用います。当初から各区分をさらに細分化することも可能ですが、最初のステップとしては、大きく特徴をつかむため3グループで進めるのが良いでしょう。ここでコミュニケーション目的に対応するKPIの現状(図の黄色いセル)を、グループ毎にインプットしていきます。調査データなどが入手可能であれば数値を記載し、もしないようであれば、定性的情報や仮説を用います。すなわちこれは将来的な調査課題(設計)の明確化にも繋がります。
さてグループを横断した全体的なKPI達成のためには、どこまでコミュニケーション・ターゲットを広げる/狭める必要があるでしょうか?これはセールス目標達成のために、「購買頻度増」が必要なカテゴリーか、購買サイクルの都合上「実購買人数増」が必要なカテゴリーか、などにもよるでしょう。
この(1)セグメンテーションと現状認識、(2)コミュニケーション目標(KPI)とのギャップ確認、(3)セールス達成へのシナリオ検証は、適切なターゲット・オーディエンス設定のための一連の循環サイクルです。ケースによっては何回も検証ループを繰り返し、更なるセグメンテーションや、グループの連結が必要になります。このプロセスに基づき、市場データ分析やワークショップなどを繰り返すことにより、戦略的判断(ターゲット・オーディエンスの設定)を導きます。
さてターゲット・オーディエンスの設定に基づき、彼らの属性や特性、ブランドとの関係性をより深く理解し、メッセージ開発やメディア戦略立案への洞察を行う必要があります。次回の記事にて以降のアプローチのご紹介をいたします。
文責:小澤 啓一/ディレクター
より詳細な情報をお求めの方は、spiindex@spi-consultants.netまでご連絡下さい。
<本レポートの引用・転載・使用に関する注意事項>
- 掲載レポートは当社の著作物であり、著作権法により保護されております。 本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。
(例:株式会社エスピーアイの分析によると…) - 記載情報については、弊社による現時点での分析結果・意見であり、こちらを参考にしてのいかなる活動に関しても法的責任を負う事はできません。