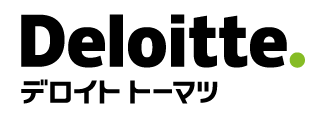SPI REPORT
マーケティング・コミュニケーションにおける意思決定
企業の合理的かつ定量的な意思決定をサポートするべく、オペレーションズリサーチ(OR)の重要性がうたわれてから久しく時間が経っています。その概念や手法はマーケティング・コミュニケーション領域にも用いられてしかるべきですが、その浸透は充分とは言い難いのが現実でしょう。
なぜORがそれほどマーケティング・コミュニケーションに反映されづらいのかを検討してみると、以下のような理由が導かれます。
- そもそも数理的なモデルを構築できるほどデータを蓄積していない (調査をしていない)
- 調査をしていてもそれは過去活動の結果測定にすぎず、未来志向の解釈をしていない (PDCAの未定着)
- 計量的なアプローチや構築された数理モデルなどが肌になじまない (数字/数学アレルギー)
- 不確実な未来に対し、過去データから導かれた推論を躊躇してしまう (調査への無力感)
- 自身の経験や勘を強く信頼し、相反する調査結果などが出た場合に信じることができない (過剰な自信)

個人的な経験からも、消費者や顧客の心理を扱い、表現戦略を伴う「広告」などの領域では、特にこれらの傾向が強いと感じています。また様々な活動に「革新性や創造性」(≒プロダクトアウト型発想)が求められることが多いマーケティング・コミュニケーションでは、どうしても過去データや調査結果が、将来の戦略策定や意思決定と切り離されてしまうということがあるのでしょう。
このあたりは、意思決定の行動科学を記したアンゾフやサイモンが述べているとおり、「不規則性が強く創造力を求められるため、構造度の低い問題(コンピュータが計算するようなものではない課題)」の特徴そのものといえます。
しかし中長期的にビジネスの命運を握るブランド・アイデンティティの構築に強く関与し、そのコストボリュームからもステークホルダーへの説明責任が強く問われるマーケティング・コミュニケーションにおいて、これは「しかたがない」で済まされるものではありません。
例えば、アメリカではCEOの36ヶ月に対して、CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)の平均在任期間は2年弱と言われています。この原因のひとつは、やはり意思決定プロセスの不透明さ(充分な吟味の欠如や、責任範疇の定義の曖昧さ)によるものなのではないでしょうか。そしてこれは最終的にはブランドの継続的成長を損ねる可能性が高いと考えます。

マーケティング業務の専門・分業化および情報量拡大が進み、網羅的に意思決定のプロセスを把握しコントロールすることが難しくなってきているのは事実です。しかしながら、現在マーケターに求められるスキルや意識として、物事を俯瞰する力(大局観)とともに、『情報への柔軟性と、意思決定の分岐点を予め設定するシナリオ構成力』があると感じています。
目標達成の結果論でビジネスを語るのは至極当然ですが、それだけではやはり継続的成長は望めません。「ベストなチョイスをしているか/していたのか」という事前・事後のコンセンサスによって、結果/評価への観点や将来への知見獲得が、全く異なるからです。
そしてその様々な可能性やリスクを判断する要素のひとつがORです。それをマーケターの信念や経験などに基づく仮説と並列で考慮することで、よりその判断への説得力が増すのではないでしょうか。言い換えれば、「ベスト」を選ぶ選択肢をORからも導く程度の感覚だと「知覚障壁」が低くなると思われます。プロスペクト理論に代表されるように、経済人でない人間(消費者)の判断は多分に感情に左右されますし、ビジネス現場における我々の意思決定もまたしかりです。それを踏まえたうえでのより綿密で網羅的な意思決定こそが、将来のブランドへの資産となるはずです。
曖昧で属人的であったマーケティング・コミュニケーションの意思決定プロセスをいかに構造化していき、ステークホルダーを巻き込んで妥当性のステップを踏んでいけるか、そこが私たちの仕事の醍醐味であると考えております。
より詳細な情報をお求めの方は、spiindex@spi-consultants.netまでご連絡下さい。
<本レポートの引用・転載・使用に関する注意事項>
- 掲載レポートは当社の著作物であり、著作権法により保護されております。 本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。
(例:株式会社エスピーアイの分析によると…) - 記載情報については、弊社による現時点での分析結果・意見であり、こちらを参考にしてのいかなる活動に関しても法的責任を負う事はできません。